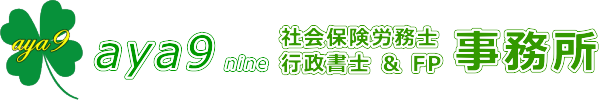将来資産の作り方・取り崩し方セミナー(投資教育)
全国社会保険労務士会連合会が認定した高度年金・将来設計コンサルタントが、公的年金のこと、税金のこと、相続のことも交えながら、誰にでもわかりやすい将来資産の作り方・取り崩し方セミナーをいたします。
セミナー実績(公的機関のみ)
- 金融機関では教えてくれない! NISAやiDeCoを利用した資産のつくりかた(2024.5/川西市川西公民館金融講座)
第1回 NISAつみたて投資枠やiDeCoにおける投資信託の選び方
第2回 NISA成長投資枠における投資信託などの選び方 - はじめての資産運用とNISA、iDeCo(2023.11/能勢町役場)
- 人生100年時代のマネープランと新NISA制度について(2023.11/川西市川西公民館金融講座)
- 未来のためのNISA&資産運用口座(2023.11/枚方市立牧野生涯学習市民センター)
- NISA、iDeCo、長期・積立・分散投資(2023.7/枚方市教育委員会)
- ライフプランと金融商品の基礎知識(2023.7/枚方市教育委員会)
- シニア世代のためのライフプランと金融商品の基礎知識(2023.1/枚方市消費生活センター)
目次
NISAやiDeCoを活用した将来資産作り方・取り崩し方セミナー
年代別セミナー
20代から40代向け
具体的なセミナー内容
- NISAと確定拠出年金(企業型DC、個人型iDeCo)、どちらを選ぶ?
50代から60代向け
具体的なセミナー内容
- 人生100年時代は資産運用をしながら長期・分散の取り崩し
- 税制から考える公的年金とNISAやiDeCoの出口戦略
経験別セミナー
初級者向け(初めての投資)
具体的なセミナー内容
- インフレ期におけるライフプランとマネープラン
- 長期・分散・積立投資が資産形成に有効な理由
- NISAと確定拠出年金(企業型DC、個人型iDeCo)の特徴
- 初めてのNISA・初めてのiDeCo 金融機関の選び方、申込みの方法
中級者向け(少しだけ投資経験あり)
具体的なセミナー内容
- 投資信託の選び方
- 株式投資信託、公社債投資信託、不動産投資信託(リート)それぞれのリスク要因
- 指数・指標にはどのようなものがあるか
- 塵も積もれば山となる 長期投資には大事な信託報酬
- 証券投資に係る税金、相続が発生したときの税金
- 運用実績データの活用

企業型DC(確定拠出年金)の投資教育
約40社に企業型DCの導入実績がある講師が、貴社の年金規約に即したオーダーメイドの投資教育を行います。
加入時の投資教育の目的
加入直後でも運用商品や掛金額の指示ができるよう、以下を目的に、基礎的な事項を中心とした教育を行うことが効果的です。
- 確定拠出年金(DC)制度における「運用の指図」の意味を理解すること
- 具体的な資産配分を自分で行えること
- 運用による収益状況の把握ができること
加入後の継続的な投資教育の目的
加入時に得た基礎的な知識からのステップアップの機会として、また制度への関心をさらに高めるためにも、加入後も定期的かつ継続的に教育を行う場を設けましょう。
以下につながるような内容であると効果的です。
- 確定拠出年金(DC)が公的年金とともに老後の生活をさせるものになること、将来のライフプランやそれに伴うマネープランを意識し、適切な運用となっているかの確認を促すこと
- 運用実績データを活用することで、運用商品に関する、より実践的で効果的な知識の習得理解すること
- 加入時に得た基礎的な知識のスキルアップや未習得事項のフォローアップを行うこと
退職時の投資教育の目的
- 退職などで資産を移換(ポータビリティ)するための選択肢
- 定年後の資産の運用方法、取り崩し方
【参考】厚生労働省HP「確定拠出年金の投資教育」
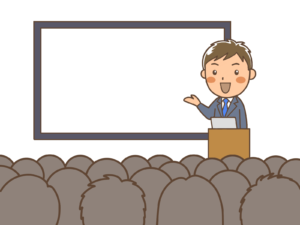
セミナー料金(集合研修)
1コマ(2時間)の場合 6万円
2コマ(4時間)の場合 10万円
(土日も同じ料金です。)
1コマ目は投資初心者向け、2コマ目は中級者向けの構成にすれば、従業員それぞれが自分のレベルに合ったセミナーを受講することができます。
また、同じ内容のセミナーを午前と午後に開催する構成にすれば、業務に支障が出ないように従業員の受講を分散させることができます。
なお、大阪駅を起点とする交通費+遠方の場合は宿泊費を別途申し受けいたします。